2.アソシエイト
印刷日本人の英語力と実学について
2025-04-11
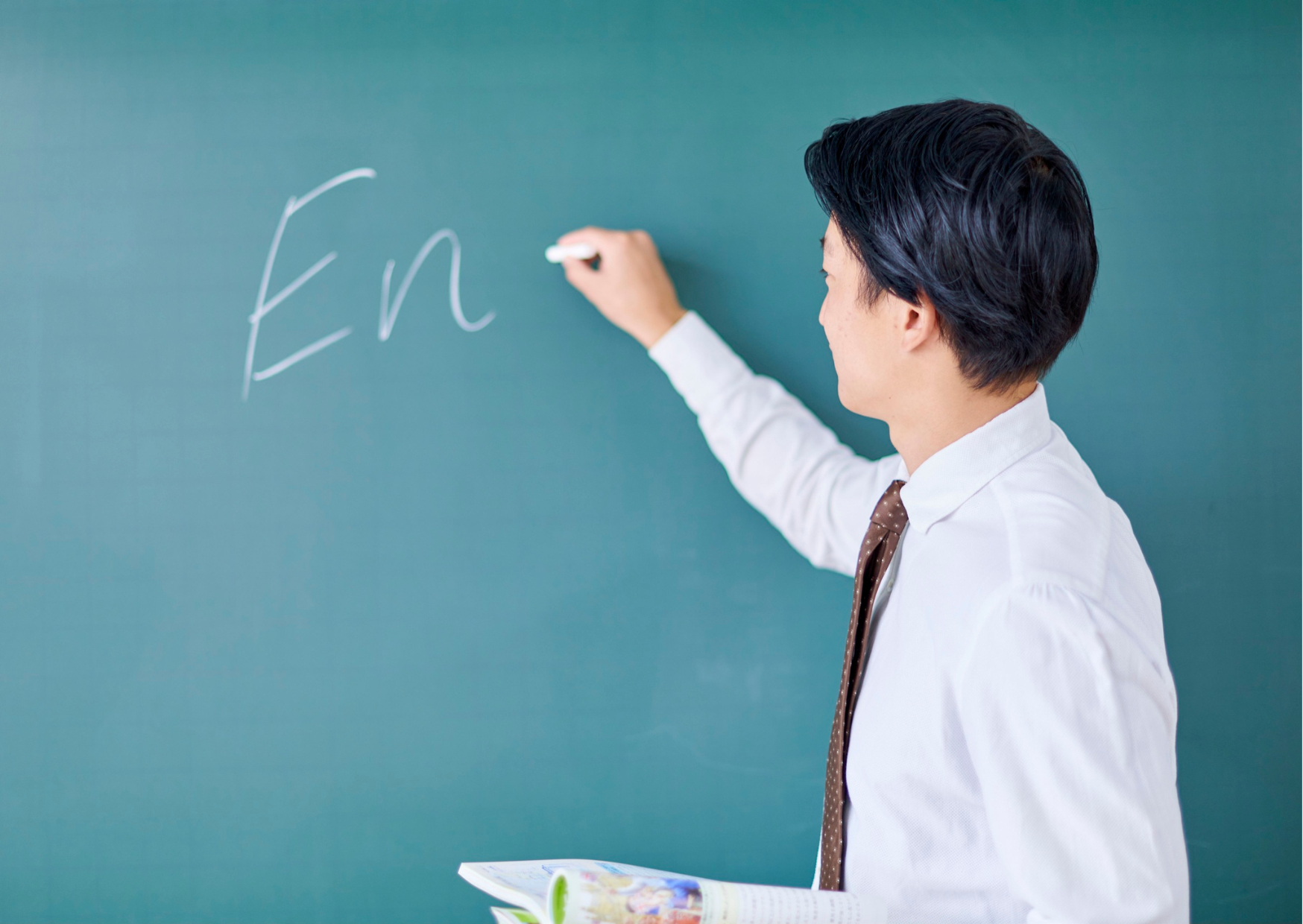
留学で感じた日本人の英語力の低さ
日本人の英語力に低さが叫ばれてかれこれ何十年経つだろうか。少なくとも私が高校生の頃(約20年前)から既にそう言われていたことを記憶している。今もOECD比較など様々な国際比較で日本人の英語力の低さが強調される記事を毎年のように目にする。私は2022年から1年イギリスに留学したが、留学先のクラス200人は50か国ほどの生徒で構成されており非常に多様性に富んでいた。結論から言うと、その中で英語力を国単位で比較したら日本人の英語力は群を抜いて低かった。これに私を含む日本人はまず出鼻をくじかれた。留学した日本人は皆日本を代表する大学を卒業した人ばかりだったが、皆が現実を突きつけられた思いだったと思う。アメリカ人やアジア人等からも率直に「なんで日本人ってこんなに英語力が低いの?」と純粋な疑問として聞かれることも何度かあった。一方、中国やアジアからの留学生はどうだったかというと、彼らは日本人と比べはるかに流暢だった。これにはいくつか理由があると感じた。一つは、そもそも日本からの留学生の大半は会社からの派遣制度を活用して留学に来ており、いわゆる中級層から留学に来ていることと、それに比べ中国やアジアからの留学生は社費で来ているという人はほとんどおらず、それでも高額な留学費用を賄える彼らの多くは富裕層の出身であることだ。彼ら彼女らの多くは学部の時点で英米の大学に進学し、4年間英語の中で暮らしているのだ。そのため母国での英語教育の良し悪しに関係なく英語力が底上げされているのだ。これはその国の教育レベルの話からは逸脱しているが、それでも日本では高校で進路を考える際に海外の大学への進学が視野に入ることは優秀な私立に通う高校生でもほとんどいないように感じる。少なくとも私の時代の日本ではそのような高校生とそうさせたいと思う親は皆無であったと思う。中国人に聞くと、海外の有名大学に入れる塾というビジネスが中国では盛んらしい。この時点で国際人を育てようという親世代の焦りやニーズの強さの違いを感じる。私の同期にはそれで起業して一財を成したという中国人生徒もいた。もう一つはシンプルに優れた英語教育を成立させている国があることだ。タイ人のほとんどが日本の東大京大に当たるチュラロンコン大学、タマサート大学からきており、彼らは英語が流暢だった。インドネシア人も同様だった。
その他科目の日本の教育水準
その他の科目に目を向けると、日本の最新の2022年時点でのPISA順位は数学的リテラシー(5位)、科学的リテラシー(2位)、読解力(3位)とOECD内でも高い順位を維持している。TIMMSという別の国際教育調査においても高ランクを維持している。そんな中、英語力はEFという英語教育を行っている会社が2011年以降毎年公表している順位で2024年時点116国中92位、前年より5位後退。アジア諸国の中でも下位レベルだ。
実学の観点
この英語力の他国との差の原因はなにかと考えるとき、いつも思うのが実学という観点だ。もちろん、日本語の英語との言語学的距離の遠さも大きな要素であると思う。ヨーロッパ言語話者が英語を習得するまでの時間と日本語話者が英語を習得するまでの時間には大きな差がある。それら変化させることができない要素を除き、改善の余地があると思うのは日本の教育におけるカリキュラムだ。理数系の科目のカリキュラムは国際順位からは成功していると言えるのではないか。それに比べると言語系の科目である国語と英語のカリキュラムはどうだろうか。他国の教育との大きな差に古文・漢文が必修科目であることが挙げられると思う。私が留学先で聞いた限り古文やさらには他国の古語を学んでいるという国はなかった(ラテン語は選択や大学の科目としては存在しているようだが、それを学ぶことで他のヨーロッパ言語の理解の役に立つという側面がある)。古文・漢文はそれらを通じて文化を未来へつなぐという役割があると思うが、全く話者のいない言語を変格活用などの細かい文法まで試験に課して高校生全員に必修で学ばせる必要はあるのだろうか。私はこのままでは国際競争力において足元をすくわれるのではないかと思う。文化継承を重視して国際競争力が衰退したら元も子もないのではと思ってしまう。古文・漢文の完全な廃止ではなく、国語という科目の中で文化として有名な作品を紹介する、選択科目にする、突き詰めたい人は大学で突き詰めるというようにして、その分英語を強化するなど、比重を変更してもよいのではないかと思う。唐突であるが、古代ギリシアで哲学が発達した背景として閑暇(スコレー)が挙げられる。哲学をするためにはその他のことが全てうまくいっていること、それによる余暇、余裕がまず必要だったのだ(それを実現したのは労働を奴隷が担っていたからだが)。ではこの言語カリキュラムと日本の英語力はというと、話者の存在しない言語の勉強やそれを通じた文化継承といった、古代ギリシアでいう哲学のような立ち位置の科目はまず英語という実用性、必要性の高い科目を高いレベルに引き上げてからに深めるというようにしてもよいのではないかと思う。自分は大学の学部選びなども社会人になって何をするのかという実学の観点で選んできたこともあり、考え方に偏りがあるのは否めないが、試す価値はあるのではないか。自分はというと、これまでは実学の観点に重きを置いて走ってきた気がするので、今後、人生の後半では閑暇(スコレー)を獲得し、実学ではないモノ・コトを追求するのもよいかもしれない。が、今はまだ実学側で走りたいと思う。
MAVIS PARTNERS アソシエイト (退職済み)








