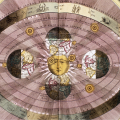1.アナリスト
印刷コンサルタントにとっての再演機会
2025-10-17

伝統とは灰を崇めることでなく、火を絶やさぬこと
―グスタフ・マーラー―
何十回目のラ・ボエーム
日、新国立劇場にてG.プッチーニ作曲『ラ・ボエーム』を観劇した。「オペラのABC(A=G.ヴェルディ『アイーダ』、B=G.プッチーニ『ラ・ボエーム』、C=G.ビゼー『カルメン』の頭文字をとってこう呼ぶらしい)」に挙げられるほど、親しみやすく、かつ、再演機会の多い作品である。例えば、世界最高峰の歌劇場の一つである米国のオペラ座メトロポリタン歌劇場の最多上演数を誇る作品は、フランコ・ゼッフィレッリ演出の同作である 。
私もオペラの世界に魅せられて以来、幾度となく『ラ・ボエーム』を観劇した。劇場だけでなく、映像や録音を含めれば、ゆうに数十回はこの作品を鑑賞している。それだけの回数を見ていても新たな発見や感動があり、演出・指揮・歌手を変えながらこの作品は100年以上の時を経てもなお愛される名作の地位を堅持しているのである。
いかなる名作も、新作であった時期があるわけで
「オペラのABC」に挙げられるような名作であったとしても、初演時の評価が高かったとは限らない。フランスオペラの名作『カルメン』の初演は大失敗だったという。また、奇しくも「オペラの三大失敗」として「オペラのABC」と作曲家を同じくする、G.ヴェルディ『椿姫』、B=G.プッチーニ『蝶々夫人』、C=G.ビゼー『カルメン』が挙げられることもある。派手に失敗し、聴衆からブーイング(現代でも、オペラ上演ではよい演奏には“ブラボー”と叫ぶ一方、よくない演奏には“ブー”とブーイングを飛ばす。私はしたことはないが)を喰らった作品にあっても、改訂・再演を重ねながら現代のオペラ上演において枢要な地位を占めるに至っている。
上記に限らず、極めて当然ながら、古典の名作であったとしても、あらゆる作品には新作であった時期が存在する。初演で絶賛された作品であっても再演機会に恵まれず、歴史の中で埋もれていった作品の方が多いはずである。この点からは、古典音楽の名作の要件は、幾度もの再演に耐える作品であると言えよう。
コンサルタントにとっての“再演”
翻って、コンサルタントにとっての再演機会について考えると、再演としてまず挙げられるのは、プロジェクトの“Phase②”、つまり継続案件である。また、継続でなくても以前のクライアントに別のテーマでご依頼いただくことも再演と言える。しかし、作曲家の歴史を想うとき、ただそのプロジェクトの再演とは、我々の報告した資料が幾度もの参照に耐えるか、とも言える。それはクライアント社内での流通(クライアントがその資料を使って説明・資料作成を行うこと)であり、もう少し時間の視座を上げるのであれば、数年後にまた“読み返したい”と思えることである。
もちろん、戦略的案件やM&Aのディールは情報の鮮度が重要なので、時間が過ぎれば情報としての価値は目減りしていく。しかし、大衆文化であるオペラも当時の流行を組みながら数多の名作を産み出してきた。情報の鮮度に胡坐をかかず、いつまでも灰とならずに燃え続ける炎のような資料を作りたいと、何十回目かの感動の涙を流しながらラ・ボエームの幕切れに想った。
MAVIS PARTNERS アナリスト 為国智博
1MET, “ACCES OPERA EDUCATOR GUIDE GIACOMO PUCCINI LA BOHÈME”
https://www.metopera.org/globalassets/discover/education/access-opera/educator-guides/
boheme-aoguide.pdf