1.アナリスト
印刷エゴは“毒”か“薬”か
2025-06-20
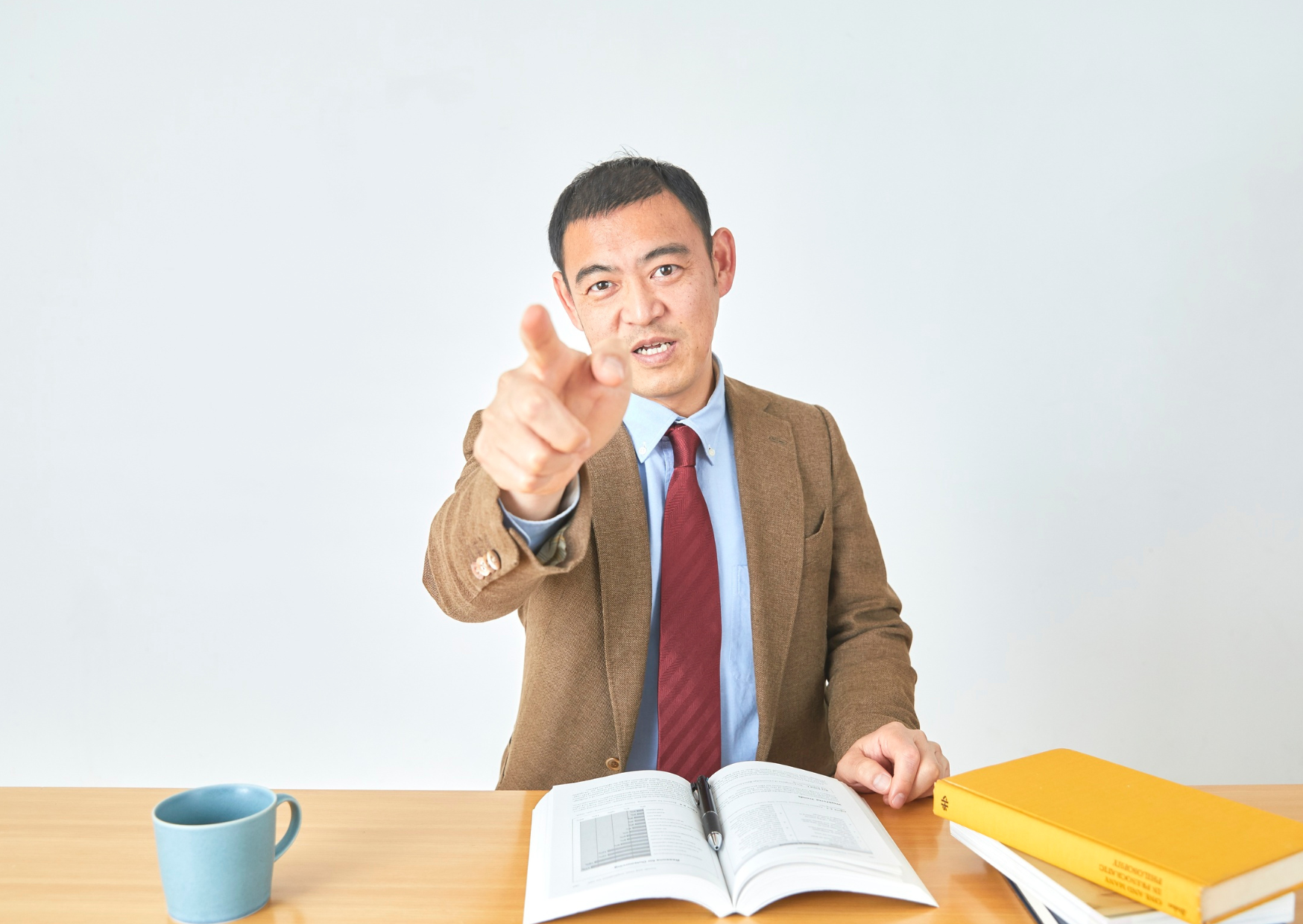
エゴが毒になった過去
通常の社会生活では、全員がエゴをむき出しにすれば秩序が簡単に揺らいでしまう。災害直後に起こる買い占め騒動などは分かりやすい。各自が「自分だけは物資を確保したい」と動いてしまった結果、店の棚は空になり、本当に必要な人に物資が届かない。エゴが同時多発的に前面に出た瞬間、社会はすぐ機能不全へ陥る。
私自身もエゴを前面に出したゆえの失敗には身に覚えがある。小中学校では「自分は教師より賢い」と思い込み、説教中に某ひろゆき氏ばりに論破をしようと反論を連発。ともに説教を受けていた同級生からは白い目で見られ、教師からは説教の追い打ちを食らった。新卒で入社した会社でも任された業務で「自分の色を出すほど評価してもらえるはず!」と暴走。資料や分析を独自の観点から“より自分ならではのもの”にしようと先輩の指示も差し置いて取り組んだものの、「そういうことじゃない」とレビューをもらい、作り直しに深夜まで向き合う羽目になった。場の流れを読み違えたエゴは毒となり、周囲の時間と信頼を奪うことを痛感した。さらに面談では「個性を出そうという姿勢は認めるがチームの中での動き方に課題あり」と明確に指摘され、自分が撒いた毒を突きつけられた。
エゴは出すこと自体がダメなのではなく、出し方が重要
ただ、その叱責の裏で先輩に言われたのは「最初から最後まで自分色で突き通そうとしているのが問題であって、個性を出そうとする姿勢そのものは面白いと思うし、悪くない」という助言だった。まずは“守破離”でいう守――チームの型を守り、土台をそろえる。具体的には社内でよく使う資料の体裁を守ることや、チームとして持って行こうとしている方向性を外さないこと。そのうえで、分析の切り口や示唆の鋭さで自分のエゴを差し込む。先輩はレビュー時に「ここまでは型、ここからが自由演技」と明確に区切ってフィードバックしてくれた。そして、そのアドバイスを守った結果、クライアントも腹落ちしてくれるものを作れるようになった。薬草が用量を誤れば毒になるが、適量なら薬として効くように、エゴも扱い方次第で価値に変わると学んだ。
エゴを正しく出すための自分ならではの方法とは?
このように、学生時代や新卒時代の反省から私はまず「型に合わせる」ことを徹底した。しかしその期間が長過ぎたせいか、今度は自分らしさを出すことが、逆に苦手になってしまっていた。実際、代表の田中から「もっと我を出したらいい」と助言を受けることもしばしばある。チームに貢献する協調性を持ちつつ、個性も示す――そのバランスは想像以上に難しい。
MAVISは「自分の名前で勝負したい」というValueに共感したメンバーが集まる会社だ。実際社内ディスカッションでは一人ひとりが独自の切り口を遠慮なくぶつけ合い、アウトプットを磨いている。そんな個性豊かな面々の姿を間近で見て、エゴの出し方は他人を真似することでは身につかないものなのだと痛感した。”日本から圧倒的ストライカーを生み出す”ということを目的に少年たちにサッカーでサバイバルをさせるという奇特な舞台設定をもつ漫画『ブルーロック』においても、主人公たちは「自分がどんな場面でゴールを決められたか」を徹底的に振り返り、再現性のある“自分のエゴ”を編み出す。他人のフォームをなぞらず、あくまでも自身の成功体験から独自の武器を掘り起こす手法だ。
同じように、私はこれまでのプロジェクトで「点を取れた」瞬間――たとえば顧客の意思決定が一歩前に進んだ場面や、洞察が議論の方向性を変えた場面――を棚卸しし、何が効いたのかを言語化していくべきだと考えている。MAVISには、週次の定例会終わりや、プロジェクトの終了後に自身のパフォーマンスを振り返る時間を必ず設けているが、そのたびに自身の反省点だけでなく、他のメンバーや上長から”良かった””価値が出ていた”と言われた場面の共通項を探し、自分に特有の”エゴ”を再現性をもった状態でいつでも出力できるように昇華させていきたい。
繰り返しになるが、エゴを前面に出し過ぎれば毒だが、的確な場面に適量で投じれば薬になる。その”用法・用量”を自分で編み出し、その精度を高めていく作業こそ、”自分の名前で勝負できる”コンサルタントになるための必須科目だと感じている。
MAVIS PARTNERS アナリスト 定永悠樹








