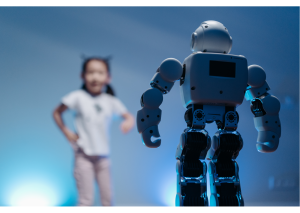AIと新卒コンサルは大差ない?!
最近、この質問をされる機会がとても増えてきました。以前、弊社コラムでも『アナリストはもう要らない』を書いた通り、生成AIが出てきてからというもの、調査や分析、構造整理、簡単な資料づくりのような作業は、もう人間が手を動かさなくてもある程度の品質で仕上がってしまいます。しかも、それなりに的を射た提案もAIが出せる時代になったと感じています。レベル感で言うと、新卒コンサルタントが数時間かけて調査・分析して考えて出してくる提案と大して変わらないのです!しかも、何をお願いしても、いつお願いしても、どんなにお願いしても、文句も言わず、疲れず、ひたむきに、頑張ってくれる。とても、便利で頑丈で健気な“若手コンサル”です。
これからコンサルタントに残る価値とは?
私もChatGPTを公私ともに使うようになって久しいですが、「こんなこともできるのか」と、日々驚きを感じています。そのうえで、「今後コンサルタントに残る価値ってなんだろうな?」とよく考えます。つまり、AIが進化しても最後まで残る「人間のコンサルタント」にしかできないことが何か、という話です。
私なりに取捨選択してまとめてみると、全部で7つは(少なくとも)ありそうだなと考えています。
まず1つ目は、「問いを立てる力」です。
AIは、問われたことに回答する力は、極めて強いことは事実です。しかし「何を問うべきか」を問うことは非常に下手。問題の構造を決めるときには、人間の意図と感受性が必要なのだろうなと思います。これからのコンサルタントの知性というのは、正解を出すことではなく、何を正解として扱うかを設計することになるのだと想像します。
2つ目は「違和感を持つ力」です。
ロジック上は正しいのに、なぜか引っかかる。整合しているはずなのに、どこかズレている。あまりに機械的な整理すぎて、気持ち悪い。そうした微細な“ノイズ”を感知できるのが人間の感覚であり、AIはこの違和感に鈍いと思います。コンサルタントは「違和感を大事にできる人」でなければならないし、安易に機械的に検討を進める人は淘汰されていくのでしょう。
3つ目は「根回しする力」です。
誰が、どの順番で、どう話すと物事が通るのか。いくらロジックが正しくても、それだけで人は動きません。組織の力学や関係性、タイミングを踏まえて“通る筋道”を設計できるのは、人間の文脈感覚があってこそ。現時点で、コンサルができる人間型ロボットはいないようですから、さすがに、AIが根回しできるのは、だいぶ先でしょう。しばらくは、この領域は人間ならではの業だと思います。
4つ目は「巻き込む力」です。
これは会議を進行するときにより感じられるものです。会議室の空気、沈黙、緊張、誰の一言で流れが変わるか。そうした場の“間”を読む力。AIに何かしらのデータをインポートすれば、分析はできるでしょうが、空気感そのものをインプットできないので、分析すらできません。そのうち、人から出される呼吸や熱から空気感を読み取って、うまいこと言えてしまうAIロボもできるのかもしれませんが、そこまで複雑な分析はできないでしょうから、これもしばらくは人間が勝てる領域だと思います。
5つ目は「信頼を使う力」です。
最終的に人が動く理由は“正しさ”ではなく“安心”です。零細企業を経営している身としては、認めたくないところではありますが、残念ながら事実です。「この会社が言うならやってみよう」とか、「この人が言うから間違いない」と思わせる関係性資本。こればかりは、いくらAIが優秀でも絶対に代替できないでしょう。人格のないAIは、信頼されることができません。たとえ、それが有名経営者のコピーAIだったとしても、「とはいっても、AIだからね」と感じてしまう感触は拭えないような気がします。
6つ目は「実行に導く力」です。
戦略を描くだけでは、コンサルの仕事は終わりません。誰が、いつ、何をするか、どの順番で動かすか。それを現実の組織や人の感情に合わせて設計し、実行まで伴走する力は、人間のコンサルしかできないと思います。AIは論理的で整った設計図を描くことはできても、人の機微や想い、現場の空気を汲み取った“生きた設計”はつくれません。そして、計画を形に変える、“手取り足取りの伴走支援”も、しばらくは、人間にしかできない仕事だと想像します。
最後、7つ目は「意味づける力」です。
意味づけとは、うまくいかなかったことや失敗したことを、そのまま“過去”にせず、状況に応じて、新しい意味を与えることです。プロジェクトの失敗を「意味ある経験」に変えることで、次の一歩を踏み出せるようにする。これは物語を再構築する力です。AIに「ポジティブに解釈してみて」といえば、それなりの回答が返ってくるかもしれませんが、そもそも、「ポジティブに解釈してみよう」と切り出せるのは、人間しかいないのです。
思考の深さで人間らしくしよう
こうして考えると、AIが得意なのは、情報と情報の関係を解析することだと言えそうです。しかし、私たちが日々扱っているのは、人と人のあいだにある曖昧さ、沈黙、緊張、ためらい、信頼、不安、そして希望。AIはこの“あいだ”を理解できません。もちろん、「理解して」と言えば、「理解しました」と応答があると思いますが、それは、共感ではなく、情報として整理できたという意味に過ぎません。AIが「正解のある世界」を処理してくれるなら、人間は「正解のない現実」を扱う存在になればいいはず。
これからのコンサルタントは、単に「考える人」ではなく、より深く感じ、考えと感情を編み合わせ、意味を創る人へと進化していかねばならないと考えています。クライアントの中にある矛盾や未整理の思いを丁寧に受け取り、構造と感情を行き来しながら、意味の奥行きを見出す。それは、情報を切り貼りする作業ではなく、人の内側にある繊細な変化を読み取り、掬い上げ、形にしていく知的な営みです。AIが“思考の速さ”を担うなら、人間は“思考の深さ”を担う。この深さこそが、コンサルタントという仕事の存在意義だと思います。
MAVIS PARTNERS プリンシパル 田中大貴