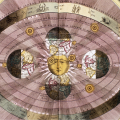1.アナリスト
印刷”自作自演”に見るガバナンスの名作~作曲家と指揮者の職能分離の歴史から~
2025-08-15

とてもうつくしい曲ですね。だれが書いたのですか?
―モーリス・ラヴェル(作曲家)―
(記憶障害に悩まされた最晩年に、自らの作曲した『逝ける王女のためのパヴァーヌ』の演奏を聴いて)
久しぶりの”自作自演”
先日、久しぶりに自作自演を見た。と、いっても普段われわれが用いるネガティブな意味合いの意味ではない。作曲家が自作品について、自ら指揮棒を振るという意味である。読んで字のごとく「自らが作曲した作品を、自らが演じる」という演奏会であった。
以前にもミュージカル『フランケンシュタイン』の衝撃と感動について拙稿を記したが、同作を作曲したブランドン・リー(同名は作曲家としてのペンネームであり、指揮者としてはイ・ソンジュンの名を用いる)が、自ら作曲したミュージカル『ベン・ハー』、『ベルサイユの薔薇』、『フランケンシュタイン』について指揮(さらには指揮をとりながらギター・ピアノの演奏まで行うという離れ業まで)するというコンサートを観劇したのだ。
ポップス音楽においては、シンガーソングライターを筆頭として、自作の歌を自ら演奏する機会も多いが、所謂クラシック音楽というジャンルにおいて、特にオーケストラによる演奏で、作曲家自らが指揮を行うという上演機会に恵まれることは少ない。
理由を考察すれば、その大部分は演奏機会の多い作品の作曲家が既にこの世を去っているという物理的な事由に帰結するのだが、近代以降においては作曲家と指揮者の職能分離進んだということもあげられる。
かつて、作曲家は演奏家を兼ね、あるいは演奏家は作曲家であった、という。モーツァルトやバッハは自らが優れた演奏家としての名声を確立しながら、作曲家としての地位を確立していった。
一方で、19世紀を代表する指揮者の一人であるドイツの指揮者ハンス・フォン・ビューロー(1830-1894年)は職業指揮者の先駆的存在であると言われる。彼の存在を筆頭として、19世紀半ば以降に「作曲家」と「指揮者」という職業は、前者は作曲を行う職業として、後者は作曲された作品を解釈し(またオーケストラの経営を含め)演奏のマネジメントを行う職業として分離していった。オーケストラという組織を指揮すること自体が一つの技術となり、こと指揮者と作曲家という職能は分離したのであった。
職能分離としての”所有と経営”
国家や企業の経営について考えるときも、同様の歴史を伺うことが出来る。
国家においては、かつて主権は君主に属し、主権と国家権力の執行は未分化のものとされていたが、近代以降において国民国家の形成と共に、主権者たる国民と国家権力は三権分立の形をとりながら分化してゆき、主権者とその代理人としての政治家・行政官という職能が分離していった。
企業においても、かつてはオーナー(個人あるいは共同する個人、または家族)による所有・執行を未分化のものとしていた企業経営は、欧米からの“所有と経営の分離”という要請もありつつ、所有を行う機関投資家などの“株主”と、執行を行う“経営者”が分化して行き、高度に技術化された職能として分離している。
もちろん、この分離は絶対のものではない。現代に至るまでも“作曲家”と“指揮者”の双方において名声を獲得した芸術家も多い(グスタフ・マーラー、リヒャルト・シュトラウス、レナード・バーンスタインなど)。また、経営の世界においても、”所有と経営の分離”は必ずしもすべての企業に当てはまるということでもなく、イーロン・マスクやマーク・ザッカーバーグなど時代の寵児たる経営者が率いるスタートアップ企業はしばし所有と経営の未分離を指摘される。一方で、これらはあくまで潮流の中の例外と捉えられるものだろう。
生き残った名作
冒頭にも記したが、クラシック音楽において“自作自演”がレアである理由は、演奏機会の多い作品の作曲家が既にこの世を去っているという要因が大きい(あるいは存命中の作曲家であっても、スターほどスケジュールが過密だという理由も上げられる)。としたとき、逆説的に今日においても演奏機会に恵まれる作品は“他演”に耐えるだけの作品であったとも言えよう。音楽史の中で、星の数ほどの作品が創造されつつも、今日において我々人類の記憶に刻まれ再演の機会に恵まれるのはそのうちのわずかな作品に過ぎない。創造主たる作曲家の手から離れても、時代を下り、指揮者・演奏家が変遷しても燦然と輝きを持ち続ける仕組みを内在させた作品こそがクラシックの名作となったのだと言える。
さて、この「創造主の手を離れても輝き続ける仕組み」という考え方は、企業や国家における統治、すなわちガバナンスの本質と重なるのではなかろうか。日本ガバナンス研究学会会長の久保利英明氏1によれば、ガバナンスとは「主権者による直接統治が不可能な大組織で、主権者と業務執行者たる代理人が異なる結果、その利害が相反する『エージェンシー問題』解決のための手法である」とされる。
源平氏は自ら打ち立てた武家政権の統治を棟梁の死後に長続きさせることはできなかった一方で、北条氏はその後に続く武家政権の統治体制を打ち立てることに成功した。織豊時代に織田信長と豊臣秀吉は天下統一をなしたものの、その死後に打ち立てた体制は瓦解したが、徳川氏はその後数百年に渡る統治体制の確立に成功した。明治維新は世界でも稀なほどの急速な日本の近代化・列強国化をもたらしたものの、明治憲法は特に行政府の立ち位置を曖昧にしてしまっていたので(なんと、明治憲法には内閣の規定がない)、立憲に携わった元勲がフェードアウトしていくにつれ、ガバナンス不全が顕在化していった。
ガバナンスを主権者と執行者間の相反を解決するための仕組みとして考えたとき、そのガバナンスが優れたものであるかを判断する一つの観点は「その創造者が去った後も機能し続けるか」といえないだろうか。強力な創造者による“自作自演”を超えて、後世にも機能することがガバナンスにおいても“名作”の条件なのではないかと思料する。
記憶障害により自ら作曲した旋律の記憶すら失った最晩年のラヴェルが、自作を聴いて「とてもうつくしい曲だ」と呟いたように、優れた仕組みは、創造主自身をも一人の鑑賞者へと変えてしまうほどの普遍性を宿すのかもしれない。現代の優れた作曲家の鮮烈な“自作自演”に触れ、クラシック音楽の名作の歴史を考えた夜、ガバナンスの“名作”に想いを馳せた。
MAVIS PARTNERS アナリスト 為国智博
1久保利英明,「企業・国家・大学のガバナンスと内部監査 主権者と業務執行者の乖離是正と内部監査」―,「月刊監査研究」, 2024年3月号